住宅の壁の一番下に付いている細長い板。これを「巾木(はばき)」といいます。
一見するとただの飾りのようですが、一体どんな役割があるのでしょうか?
■ 巾木の役割
幅木には、主に次の3つの役割があります。
① 壁と床の納まりをよく見せる
② 汚れを目立たなくする
③ 壁の下部を補強する
壁と床の境の線を直線にするのは、施工においてかなりの精度が求められます。そこで、壁と床がぶつかる部分に幅木を付けることで、境の線を隠すことができます。つまり、床材や壁材の断面が厳密でなくても、端部が直線的に納まって見えるわけです。
また、クロス貼りや塗装工事においては、巾木の上で仕上げを止める役割もあります。
さらに、壁の下部は掃除機や家具がぶつかったり、ほこりが溜まったりしやすい部分です。そのため、濃い色の幅木を打って壁を補強し、汚れを目立たなくするのです。
■ 巾木の納まりの種類とサイズ
幅木の取り付け方として、次の3つの種類があります。
① 出巾木
壁面より出っ張って付けるものをいいます。最も一般的な納め方です。
② 面巾木
壁と同じ面上に納める方法です。そのため同面巾木やフラット巾木とも呼ばれます。
③ 入巾木
壁よりも内側に引っ込んで納める方法です。そのためすっきりとした印象を与えます。
壁の下にさりげなく取り付けられている巾木ですが、実はいろいろな役割があったのですね。

みなさんは「垂木(たるき)」という言葉を知っていますか?
垂木は、勾配のある屋根を持つ住宅に欠かせない部材です。
今回のコラムでは、その特徴や役割についてご紹介します。
垂木とは?
垂木とは、屋根の一番高いところにある棟木から軒桁にかけて斜めに打ち付ける部材のこと。棟から軒先に向かって、上から下に垂れていることから“垂木”と呼ばれています。
垂木の役割
垂木の役割は、主に2つあります。
①屋根面の荷重を受けて支える。
②野地板(のじいた)を張り付けることで、棟木と軒をつなぎとめる。
屋根をふくための下地である野地板(ベニヤ板)は、あまり強度はありません。
そのため、垂木と固定することで屋根の強度が増し、雨風や歪みに耐えることができるのです。
垂木の取り付け
固定する間隔は一般的には45.5cmですが、30.3cmで設置することもあります。
在来工法、ツーバイフォー工法といった施工方法の違いによって垂木の固定方法は変わりますが、中には金物を使用する、長めの釘を使用して固定するといった方法があります。
垂木の断面サイズは、軒の出の長さや屋根材の種類などによってさまざまです。下記は目安です。
● 標準的なサイズ 幅45mm×高さ60mm
● 軒の出が長い屋根の場合 幅45mm×高さ75mm
● 重い屋根材の場合(強度を高めるため) 幅60mm×高さ75mm
屋根材を支える垂木、普段はあまり目にすることのない部分ですが、重要な役割を担う縁の下の力持ちなのですね。

現在の一般木造住宅の柱には、3寸角(90mm角)、3寸5分角(105mm角)、4寸角(120mm角)の柱がよく使われます。
3寸=30mm×3=90mm
3.5寸=30mm×3.5=105mm
4寸=30mm×4=120mm
また、柱の背中が割れているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。
これはわざと入れたもので、「背割り」といいます。
乾燥・収縮して思わぬところに割れが入らないようにするためのもので、木の芯を含む芯持ち材の柱には必ず背割りをします。
集成材の場合は割れの心配はないので背割りは入れません。

サブロク板2枚をあわせた正方形の面積は「約1坪」です。
サブロク板2枚の面積=畳2枚分=6尺四方=1818mm角≒1坪
建築面積や延べ床面積も「坪」を使って表現をします。
“1坪=サブロク板2枚=畳2枚”は、あくまでも目安の数値になります。

サブロク板の大きさは、「襖」や「障子」とほぼ同じ寸法です。
どちらも和室に使われるものですが、
下の溝付きレールを敷居、上の溝付レールを鴨居と呼び、敷居上端から鴨居下端まで、開口の有効高さを内法高(うちのりだか)といいます。
内法高≒6尺=1間(1818mm)
つまり、
襖・障子の大きさ≒サブロク板=910mm×1820mm
となります。

サブロク板の大きさは、日本人によく馴染みのある「畳」とほぼ同じ大きさです。
完全に同じものもあれば若干異なる事もあり、
京都を中心とした西日本で広く用いられた「京間」、関東や東北・北海道で主に使われている基準のひとつ「田舎間」など、地方によって基本寸法の取り方に違いがあります。
そのため大きさや作り方にまで違いがあります。
つまり、
畳の大きさ≒サブロク板=910mm×1820mm
日本人の住まい方は畳と深く関係しています。
その畳と大きさがほぼ同じサブロク板は、昔からの伝統的な資材と言えますね。
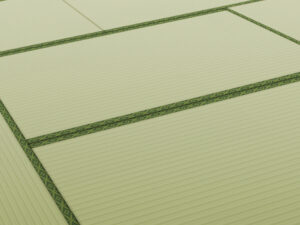
「サブロク板(ばん)」という言葉は聞いたことがありますか?
一般的にはあまり馴染みのない言葉ですね。
「サブロク板とは3尺×6尺の大きさの板」です。
一般的に売られている板はこの、サブロク板が多いです。
そこで「尺」がどのくらいの長さかというと下記のとおりです。
これは基本の数字でよく使う言葉でもありますので覚えておくと便利です。
1尺 … 約303mm
3尺 … 約909mm
6尺 … 約1818mm
日本の木造住宅の基本寸法となっており、多くの日本の伝統的な建物にはこのサブロク板が使われています。
ちなみに、正確には3尺(909mm)×6尺(1818mm)ですが、あまりに細かいので
910mm×1820mmに製材されて売られています。
 〒396-0009 長野県伊那市日影336
〒396-0009 長野県伊那市日影336